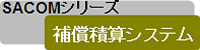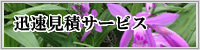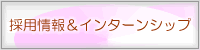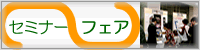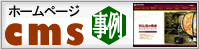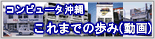マルチメディア事情視察報告書1997年10月
沖縄商工会議所マルチメディア委員会
先進技術は「あとまさい果報」(※注)
㈱コンピュータ沖縄 名護 宏雄
今回の視察研修(※1997年)は、沖縄商工会議所管内のマルチメディア社会への対応についての調査・研究ということでありました。アジア諸国のマルチメディア構想の取組みや、進歩状況等を勉強し、各委員の基本認識、知識の共有化を測った上で、討議を深めるのが狙いでありました。
平成8年10月から視察研修の検討を開始し、訪問先をマレーシア、シンガポール、台湾経由と決めスケジュール調整を進めました。とかく評判の悪い日本の「物見遊山」的な視察ツアーとは違った内容あるものにしようということで、ホームページのアドレスを調べ、MSC(マルチメディア・スーパー・コリドー)と、シンガポール・ワンの資料を取り寄せました。内容が英語なため、翻訳ソフトを活用しましたが、迷訳のためあまり役に立たなかったようです。
事前情報としてNTTの嘉陽支店長、県の国際交流課、外務省沖縄事務所の松永総合調整官等にご協力をいただきました。又、同行のメンバーの事前研修ということで沖縄県トロピカルセンター、NTTコザ営業所、㈱コンピュータ沖縄でインターネットホームページの活用方法の、勉強会も実施しました。
マレーシアでは、NTTクアランルプール事務所で堀田明男所長から説明を受けました。1991年に発表された「ビジョン2020」を具現化したプロジェクトが、「MSC(マルチメディア・スーパー・コリドー)」で1996年10月からスタート、首都クアランルプールと新国際空港を結ぶ地域に「特別地区」(東西15km、南北50kmの長方形でシンガポールより大きい)を設け、その中にサイバージャヤ(研究都市)とプトラジャヤ(電子政府)を建設、そこに世界最先端の、マルチメディア実験都市を構築する構想である。
プロジェクトにはマスタープランの段階からNTTも参加し、マハティール首相の諮問機関「国際アドバイザリーボード」には、マイクロソフトのビル・ゲイツ、オラクルのラリー・エリソン、NTTの宮津社長、富士通の関澤社長らが名を連ね、世界中の大企業をまきこんだプロジェクトとして、期待と夢のある壮大な構想でありました。
シンガポールでは、国家コンピュータ局の副長官、荘 建国さんの説明を受けました。
国土面積600㎢、人口300万人の小国、沖縄の中南部の面積(石川市まで)に300万人の住む人口過密の都市国家がシンガポールであります。
1992年10月にスタートした国家プロジェクト「IT2000」の実績を踏まえ、更なる具体化へ向けたプロジェクトの1つが「シンガポール・ワン」であります。
インターネットを前提に、マルチメディア社会実現を目指す構想で、現在、全土の通信網がISDNでデジタル化が完了し、155ビット/秒のATMネットワークをバックボーンに張り巡らせ、各家庭には世界的に大きく注目されているADLS技術で、アクセス回線を今年中(※1997年)に提供予定になっております。インフラの整備は徐々に整い、今はアプリケーション構築の実験が行われ、学校教育への実験も有効性が実証され、全国へ拡大の最中とのことでありました。
マレーシアとシンガポールの構想は一見似かよっています。事前の資料調べであるいは見聞きした範囲でも、なかなか違いが理解できませんでした。今回の視察研修で現地に来て初めて自分なりに納得が得られました。
それは、シンガポールは、すでにインフラの整備が進み各プロジェクトのアプリケーションに予算の裏付けがあり、実験中あるいは実験終了のものがあります。さらに国が狭く人口が少ない為、実験の結果を短期間に全土への展開が可能であります。「小回りのきく」強さを感じました。
これに対しマレーシアは広い国土の中に、都市そのものをゼロから建築する、まだ街づくりに着手した段階であり、これからインフラの整備、アプリケーションの構築、人材の育成と、多くの課題があります。
沖縄の方言の「あとまさい」(※注)という言葉通り、技術の世界では遅い方が得をすることも多々あります。携帯電話やパソコンの技術進歩を見れば明らかであります。シンガポールの後を追い、ゼロからスタートする、規制のないマレーシアが革新的で斬新なアイディアで、大きく進展する可能性もあります。
マルチメディアの進展は革命に近い大変革が起こるということで、世界各国がその対応策を練っています。天下り先のポスト確保を優先し、縄張り争いをし、規制緩和さえ実現できない国の官僚、片や発展途上国の官僚は「情報技術の動向を見極め、法体系の整備から情報化戦略の構築」まで、誇りと秩序を持って中心的役割を担っています。
シンガポール・ワン38歳の副長官は「日本の技術に期待するものは?」との質問に対して「ナシ」の答え、念を押してほんとに「ナシ」ですかと聞いたら、笑いながら英語で「ナッシング」との答えでありました。彼ら英語圏の人間には欧米しか視野にない印象でありました。
たまたま沖縄県も「全島フリーゾーン構想」「国際都市形成構想」「マルチメディア・アイランド構想」なるものの論議の最中であります。
県の「マルチメディア・アイランド構想」も、マレーシアの「MSC」も、シンガポールの「シンガポール・ワン」もインフラを整備し、その後、アプリケーションを推進する、手順は同じであります。違いはアプリケーションの中味ではないでしょうか、どのようなコンテンツをいつまでに、デジタルデータ化していくかが問われているのではないかと思います。
マルチメディアの時代は「ベスト・ワンよりもオンリー・ワン」が大事だと聞きます。沖縄独特の歴史、地理的位置が亜熱帯であること、そこで芽生えた文化等が国内におけるオンリーワンでしょう。
「空手」「エイサー」等の芸能、高校生の「マーチングバンド」、「創作ダンス」あるいは、芸能界の安室奈美恵、喜納昌吉等が世界のオンリーワンではないでしょうか。沖縄には我々ウチナンチューのまだ気付かない沢山のオンリーワンが埋もれているような気がします。
今回の視察研修を念頭におきながら沖縄市を中心とした、マルチメディア社会実現の為の調査研究を深めていく決意であります。
(注)「あとまさい」:沖縄の方言で、後の方が有利、得をする、といったような意味。